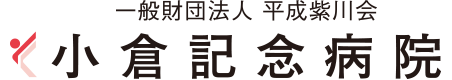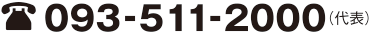泌尿器科【腎センター】
Urology腎う尿管がん
症状
肉眼的血尿(目で見てわかる血尿)をきたす例は少なく、検診等で尿潜血陽性、水腎症の異常を指摘される方が多く見られます。
尿路閉塞を起こすと水腎・水尿管症が生じ、軽度の腰背部・側腹部鈍痛が現れます。
検査
尿検査
尿細胞診
静脈性腎盂造影
CT検査
MRI検査
逆行性腎盂造影
腹部超音波検査
治療
転移がない場合は、腎および尿管すべて(尿管口までを含めて)を摘出する腎尿管全摘除術を行います。悪性度が低く表在性の尿管がんに対しては、尿管鏡による切除を行うこともあります。転移はリンパ節・肺・肝・骨などに認めます。
初診時に、すでに転移のある進行がんの場合や、術後転移が生じた場合には、膀胱がん治療の場合と同様にGC療法やMVAC療法に代表される多剤併用化学療法を行います。これは1コース3〜4週間の治療で、3〜4コース行います。骨髄(こつずい)抑制(白血球・赤血球・血小板の低下)、吐き気・嘔吐、脱毛、末梢神経障害などの副作用があります。
副腎腫瘍
症状
血圧が急に上がってきた、薬を服用して血圧の下がりが良くない、動悸がする、血糖値が高くて下がりにくい、重が急に増えてきたなどの症状があります。
検査
尿検査(ホルモン)
血液検査(ホルモン)
CT検査
MRI検査
腹部超音波検査
治療
腹腔鏡下副腎摘出術、開腹副腎摘出術
ホルモン産生腫瘍であるクシング症候群、原発性アルドステロン症そして褐色細胞腫は手術で摘出する必要があります。手術は開腹手術と内視鏡手術があります。副腎は体の奥深いところにあるため、小さな臓器であるにもかかわらず、以前の開腹手術ではお腹を大きく切開する必要がありましたが、最近では内視鏡を使った腹腔鏡手術が主流です。副腎の場合、取り出す臓器(腫瘍)が小さいのでまさに理にかなった方法です。お腹に3〜4ヵ所の穴を開けてカメラや細長い手術器具を入れて、腫瘍を剥離して摘出するという方法です。この内視鏡手術は開放手術に比べて傷が格段に小さいため、手術後の回復が早いとされています。
尿管結石・腎結石
症状
尿管結石は疝痛発作(突然に生じる激しい背部痛・側腹部〜下腹部痛)、血尿が典型的な症候です。
腎結石は血尿、背部鈍痛、検診によるエコー検査等で発見されます。
検査
尿検査
腹部超音波検査
レントゲン単純写真
静脈尿路造影検査
CT検査
治療
体外式衝撃波結石破砕治療(ESWL)
体外衝撃波結石破砕装置の1987年の導入以来、毎年200例前後の新患を治療しております。音波の一種である衝撃波を体の外から結石に向けて発射し、筋肉や他の臓器を傷つけることなく、結石のみ細かく破砕する治療です。
砂状に破砕された結石は尿と共に自然に体外に排出されます。排出までの時間は患者さんによって異なりますが、多くは数日から2週間程度です。
副作用や後遺症もほとんどなく、現在では結石治療の第一選択肢となっています。
経尿道的レーザー砕石術
尿道・膀胱を経由して尿管に内視鏡を挿入してレーザーにて結石を破砕します。砂状に破砕された結石はESWLと同様に、尿と共に体外に排出されます。
経皮的砕石術
経尿道的破砕術によって破砕な困難な尿管結石や大きな腎結石、尿管に強くはまり込んだ結石等は、背中から穴をあけ腎臓に直接内視鏡を挿入して治療を行います。
設備
体外式衝撃波結石破砕治療(ESWL)
内視鏡手術システム
内視鏡ビデオシステム
レーザー発生装置
排尿障害(前立腺肥大症など)
症状
尿が出にくい、尿がもれる、尿が出る回数が多い、尿が出る時に痛いなど
検査
腎・膀胱超音波検査
膀胱機能検査
経直腸前立腺エコー
前立腺触診
治療
経尿道的前立腺切除術(TURP,HoLEP)
HoLEPは前立腺肥大症に対する新しい治療法であり、内視鏡の先についたレーザーメス で肥大した前立腺腺腫を安全・確実に切除していく手術です。これまで主流な手術術式であった経尿道的前立腺切除術(TURP)よりも出血および術後の疼痛が少なく、安全に行うことができます。さらに100mlを超える前立腺に対しても施行可能であり、サイズによらずに行えるというメリットもあります。腺腫を確実に核出するというその手術方法から再発が少ないという点も優れた特徴といえます。
萎縮膀胱拡大術
膀胱拡大術は、縮んでしまった膀胱の大部分を切除して、他の器官(小腸など)を使って拡大した膀胱を形成する手術です。
尿失禁手術
現在の当院での尿失禁手術は、これまでのTVT手術に代わり、TOT手術が主流となっています。いずれも特殊なテープにより尿道を支えて尿もれを防ぐものですが、TOT法のほうが、より自然に近い形であり、張力過剰(しめ過ぎ)の危険が少ないと言われています。また、下腹部ではなく、足の付け根方向にテープを固定するため、膀胱や腸、大きな血管を傷つける可能性が少ない方法です。
腎臓がん
症状
血尿
腹部のしこり
わき腹の痛み
検査
血液検査
尿路造影法
超音波診断
CT検査
MRI検査
治療
外科療法
腎臓は通常どちらか一方が残っていれば,もう一方の腎臓が2つ分のはたらきをするので特に問題はないとされ,原則として手術は腎摘出手術となります。
腫瘍径が大きい場合,腎周囲脂肪組織や周囲のリンパ節,同じ側の副腎をまとめて摘除する根治的腎摘除術を行ないます。
最近では,画像診断技術が進歩し,初期のがんが発見されることも多く,以前よりも腎臓の一部だけを切除する腎部分切除術が行われることが多くなりました。
これにより病腎の一部は温存されますし,全摘出と比較して再発率や生存率に大きな違いはありません。
インターフェロン、分子標的治療
インターフェロン療法とは、自分の免疫力を高めるために行なわれる免疫療法のことです。注射や点滴で投与し治療の効果は実証されているのですが、副作用があるのも特徴です。分子標的治療薬は、腫瘍細胞の増殖や血管内皮細胞の増殖にかかわる細胞内シグナル伝達を阻害することによって腫瘍の増殖を抑える薬です。
膀胱がん
症状
血尿
排尿障害
背部痛
検査
尿検査
膀胱鏡検査(内視鏡検査)
超音波診断
CT検査
MRI検査
治療
内視鏡手術
表在がんでは,尿道から内視鏡を挿入し、電気メスやレーザーにてがんの切除を行います。
膀胱部分切除術
以前は膀胱の一部のみ切除するという手術もおこなわれていましたが,再発や転移しやすいことがわかり,現在ではあまりおこなわれていません。
膀胱全摘除術
浸潤がんの場合は膀胱全摘除術がおこなわれます。膀胱のすべてと前立腺や精嚢,尿道を摘出し,骨盤内のリンパ節を摘出(骨盤内リンパ節郭清)します。膀胱がなくなるので、膀を使い尿をおなかの外に導く回腸導管や尿感をおなかの外に出す尿管皮膚瘻術、腸を使用した人工膀胱造設術を併用します。
前立腺がん
症状
(夜間)頻尿
排尿困難・残尿感
尿意切迫感
PSA検診で異常指摘
検査
直腸指診
PSA, phi(血液)検査
MRI検査
(経直腸的)超音波検査
前立腺針生検
CT検査・骨スキャン検査
治療
ロボット支援下前立腺全摘除術
当科では、限局性(転移がなく前立腺内に留まっている)前立腺がんに対して、根治療法の適応があれば、積極的にロボット支援下前立腺全摘除術を施行しています。
ロボット支援下前立腺全摘除術は、創(傷口)が小さく、術後の痛みが軽く、回復が早いとされています。ロボット手術では、拡大した鮮明な3次元画面を見ながら、ロボット・アームを使用することにより、非常に正確で繊細、さらには複雑な手術操作が可能となります。これにより、がんを確実に取り除き、出血や他の臓器損傷などの術中合併症を低減することができると考えられます。加えて、尿禁制(尿もれが少ない)や勃起などの機能温存が期待できるようになります。
精巣がん
症状
陰嚢の腫れ
治療
高位精巣摘除術
高位精巣摘除術とは、陰嚢ではなく足の付け根の鼠径部を切開し、精巣に向かう血管をまず結紮し、癌細胞が手術操作によって散らばらないようにしてから、精巣、精巣上体、精索を一塊として摘出します。
精巣摘出後、通常はそのまま何もしないで観察します。CTなどで転移がないとされても1〜2割では目に見えない転移がすでにあって、そのような場合は1〜2年以内に大きくなって再発として認識されるようになります。そのため転移の出現を予防するための治療を追加することもあります。予防的治療を追加しない場合は術後約1〜2年の間は毎月のマーカーチェックと約3ヶ月に1回のCT、あるいは腹部超音波検査で細かく経過観察することで早期発見早期治療をすれば再発症例でも根治率がほぼ100%と良好です。