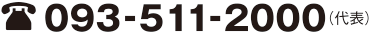ブレイン・ハート外来
brain・heart clinic
症状
出血リスクが高く抗凝固薬の服用が難しい患者さん、脳梗塞の原因が潜因性か特定できない患者さん

心疾患が関与する脳卒中を予防
近年、左心耳閉鎖術WATCHMANや卵円孔開存閉鎖システムPFOオクルーダーの登場によって循環器内 科領域での脳梗塞予防が可能になり、循環器内科と脳神経外科2つの診療科の連携は、脳梗塞のリスク を低減するために重要な意味を持つようになりました。そこで当院では出血リスクが高く抗凝固薬服用 が難しい患者さんや脳梗塞の原因が潜因性か特定できない患者さんに対応するためにブレイン・ハート 外来を新設し、卵円孔開存の有無など専門的に検査するできる体制を整えました。検査結果は、脳卒中 専門医と循環器内科専門医によるブレインハートカンファレンスで協議され、患者さん一人ひとりに適 した治療を選択できる体制となっています。
受診方法
かかりつけの先生とご相談のうえ、当院の医療連携室を通じてご予約をお願いします。
診察日
【左心耳閉鎖】
毎週火曜日/担当医:福永 真人
【卵円孔閉鎖】
毎週月曜日・水曜午後/担当医:白井 伸一
毎週水曜日/担当医:石津 賢一
ブレインハート外来の対象疾患と治療法
● 卵円孔開存を有する潜因性脳梗塞 → 卵円孔開存閉鎖術「PFO closure」
● 心房細動に抗凝固療法中で脳出血 → 左心耳閉鎖術「WATCHMAN」
● 心房細動に抗凝固療法中で再発性脳梗塞 → 左心耳閉鎖術「WATCHMAN」← (HAS-BLED score次第)
● 心房細動に抗凝固療法中で出血性合併症 → 左心耳閉鎖術「WATCHMAN」

外来日

地域の先生方向けのQ&A【卵円孔開存閉鎖 (PFO closure) 】
ブレイン・ハート外来の窓口は循環器内科なのか脳神経外科なのか?
循環器内科で対応します。各種検査の後に、脳神経外科医とのブレイン・ハートチームカンファレンスで治療方針を総合的に検討します。必要な場合は、脳神経外科対応に移行します。
ブレイン・ハート外来の対象はどんな疾患・治療なのか?
PFO closure と左心耳閉鎖 (LAAC) を念頭に、以下の患者様を対象としております。
卵円孔開存を有する潜因性脳梗塞 (PFO closure)
心房細動に抗凝固療法中で脳出血を起こした症例 (LAAC)
心房細動に抗凝固療法中で再発性脳梗塞を起こした症例 (LAAC)
心房細動に抗凝固療法中で出血性合併症を起こした症例 (LAAC)
PFO closure が対象となる典型的な患者像とは?
若年で脳梗塞を起こし、潜因性脳梗塞と脳卒中専門医に診断され、循環器内科医によって PFO を通じた右左シャントが証明された方が典型的な患者像です。
潜因性脳梗塞患者を紹介したいが、年齢制限はあるか?
特にありません。PFO closure に関しては原則60歳未満の患者に適応があるとされていますが、60歳以上でも脳梗塞を繰り返す場合や他に原因が考えにくい場合などではブレイン・ハートチームカンファレンスで総合的に検討した結果、治療適応と判断する場合があります。
脳梗塞ではなく一過性脳虚血発作(TIA)の場合はどうすればよいか?
潜因性のものが疑われる場合にはご紹介下さい。ブレイン・ハートチームカンファレンスで治療方針を検討し、治療適応と判断する可能性があります。
他院で脳梗塞と診断された患者がいるが、潜因性かどうかわからない。ブレイン・ハート外来に紹介してよいか?
ご紹介下さい。各種情報の収集、追加検査等を行い、ブレイン・ハートチームカンファレンスで総合的に治療方針を検討します。
潜因性脳梗塞と診断された患者がいる。バブルテストのみお願いしたいが、可能か?
可能です。ぜひご紹介下さい。
初めて脳梗塞となった患者がおり潜因性と考えられる。初回の脳梗塞は治療適応か?
卵円孔開存があれば、初回の脳梗塞で治療適応です。ぜひご紹介下さい。
ラクナ梗塞の診断がついているが、PFO closure の適応はあるか?
ラクナ梗塞の場合は PFO closure の適応はありません。
下肢静脈血栓 (DVT) の存在は PFO closure に必須か?
必須ではありません。潜因性脳梗塞と診断され、PFO を通じた右左シャントが証明されれば、閉鎖適応になり得ます。
塞栓症の既往はないが、卵円孔開存の指摘がある。予防的な閉鎖の適応はあるか?
塞栓症の既往がない場合、閉鎖適応はありません。卵円孔開存は人口の20%以上に存在するとされていますが全員が塞栓症を起こすわけではないため、あくまで症状を有した方が閉鎖適応となります。
特にハイリスクな PFO の特徴は?
シャント量が多い、心房中隔の動揺の幅が大きい、PFO のトンネルが長い、Eustachian弁や Chiari網があるまたはPFO と心房中隔の角度が浅いなどがハイリスクPFO とされており、経食道心エコー図検査で診断します。
バブルテストで脳梗塞を誘発しないか心配。
バブルテストはガイドラインにも記載れた必須の検査法で、正しく行えば脳梗塞を誘発することはありません。
潜因性脳梗塞と診断された患者がいる。バブルテストのみお願いしたいが、可能か?
可能です。ぜひご紹介下さい。
バブルテストでは経食道心エコー図検査も行うか?非常に苦しいと聞いたが?
まず通常の心エコー図検査 (経胸壁心エコー図検査) でバブルテストを行い、続いて経食道心エコー図検査を行います。当院で行う経食道心エコー図検査は原則として全例で鎮静剤を使用しており、検査中の苦痛はほとんど感じないように配慮しております。
他院で以前バブルテスト陰性と出たが、潜因性脳梗塞を繰り返している。もう一度バブルテストを行う意義はあるか?
バルサルバ負荷が不十分な場合、本来右左シャントが存在してもバブルテストが陰性になってしまうことがあります。決して侵襲の高い検査ではありませんので、ご紹介頂けましたらいつでも再評価させていただきます。
カテーテル的ではなく外科的にPFOを閉鎖することもあるか?
ございます。ただし、解剖学的にデバイス留置不可能と判断した場合のみであり、大多数の患者がカテーテル治療をお受けになられています。
PFO closureの入院期間は?
通常、治療の翌日から歩行を開始し、翌々日には退院となります。
PFO closure後は、すぐに抗血栓薬を中止してよいか?
留置したデバイスへの血栓付着予防として、原則として半年間の抗血小板薬2剤併用をお願いしておりますが、出血リスクの高い患者においてはその限りではありません。退院時に診療情報提供書に明記させて頂きます。
PFO closure後、CTやMRI検査の制限はあるか?
特に制限はございません。
地域の先生方向けのQ&A【左心耳閉鎖 (LAAC) 】
なぜ左心耳を閉鎖するのですか?
左房の端っこにある左心耳は盲端になっており、非弁膜症性心房細動患者さんでの血栓の9割以上は左心耳に生じるとされます。抗凝固療法が難しい方では左心耳を閉鎖することで血栓形成を予防し、抗凝固療法を安全に中止できるようになります。
どのような方法で行う治療ですか?
全身麻酔・透視・経食道心エコー図ガイド下に右大腿静脈からカテーテルを挿入して治療を行います。順調に進めば 30分前後で終了します。
抗凝固療法は中止できても、抗血小板療法は必要と聞きましたが?
原則としては抗凝固薬を中止して抗血小板剤は継続しますが、出血リスクに応じて柔軟に対応します。
抗凝固療法は治療後、すぐに中止できるのですか?
術後には一定期間の抗血栓療法を行う必要があります。レジュメ(種類と期間)に関しては、出血リスクと梗塞リスクを天秤にかけて個別化して対応しております。
術後の外来通院の頻度や検査内容について教えて下さい
術後は通常のリスクであれば、4ヶ月後に再診し造影剤を用いたCTでの評価を行います。腎機能によっては1泊2日の入院経食道心エコーを行うこともありますが、以後は年に1回程度の通院で大きな検査はありません。
脳梗塞を予防する治療なのですか?
脳梗塞の予防としての効果は抗凝固療法の継続と同等程度とされていますので、抗凝固療法で特に困っていない方は、抗凝固療法以上の脳梗塞予防効果はありません。但し、抗凝固療法をおこなっているにも関わらず、脳梗塞を繰り返す際には、有効なこともありますので、ご相談ください。
HAS-BLED スコア 3点以上の出血リスクが適応とききました。出血とはどの程度ですか?
日本循環器学会からの適正使用指針では、出血イベントとして入院での治療介入を要するもの、輸血を要する程度の貧血や脳出血などの医学的に重大な出血が大出血とされ、リスクスコアに関わらず適応となります。リスクスコアの出血傾向(HAS-BLEDスコアの”B”に当たる)では、大出血には該当しないものの、医学的に対応を要する(外来受診や血液検査を要する)ものが小出血とされます。貧血の存在も含みます。
点状出血のような皮下出血は、出血としてカウントしますか?
点状出血のみでは出血カウントには含みませんが、抗凝固療法による出血傾向のために外来受診をして処置を行う程度では上記の小出血に含みます。
血痰は出血としてカウントしますか?
血痰も受診や休薬をを要するレベルの出血であれば、小出血に含みます。
血尿は出血としてカウントしますか?
血尿も受診や休薬をを要するレベルの出血であれば、小出血に含みます。
脳出血の既往は程度に関わらず出血としてカウントてよいですか?
脳出血は既往であっても大出血に含まれますが、MRI検査の中で”微小出血(T2*強調画像)”と呼ばれるものや、脳梗塞に付随した出血性梗塞は出血イベントに含みません。
大きな出血の既往は、例えば20年前のものでもカウントしますか?
基準としては含みますが、例えば出血の原因が除去可能なもの(胃ポリープからの出血ですでに切除済み)か除去不可能なもの(大腸憩室出血)では医学的な重要度は異なります。実際には20年前の出血の単回のエピソードで最近困っていなければ、要相談となります。
LAAC は出血した方の治療、というイメージが強いのですが、実際に出血イベントは全くなくても、HAS-BLED 3点以上の「ハイリスク」の段階でも治療適応がある、という理解でよいのでしょうか?
将来的にはいつ出血性合併症を起こすかの予測は困難ではあるのですが、HAS-BLED 3点の患者さんの年間大出血発症リスクは 4%弱であり、10年での累積発症リスクなどを考慮すると、ハイリスクの方でも転ばぬ先の杖として適応があると考えます。
人工弁置換術のためにワーファリンを内服中です。適応になりますでしょうか?
人工弁置換術の中で”機械弁”では、血栓弁の予防目的にワーファリン使用が推奨されており、LAACの適応にはなりません。生体弁置換術の術後3ヶ月以降であれば適応の可能性がありますが、僧帽弁狭窄症を基礎疾患とした場合には”弁膜症性心房細動“となるため、現在僧帽弁狭窄がなくても左房の著明な拡大を認めるケースが多く、適応としないこともあるためご相談ください。
脳神経外科医です。心房細動で抗凝固療法中で、脳出血を起こした方は多くの場合は高血圧もお持ちです。こうした方はみな LAACの適応でしょうか?
脳出血既往の2次予防として高血圧のコントロールはもちろん大切です。但し、血圧コントロールを適切に行なったとしても微小出血などのハイリスクの方では再発率が高いのが現状です。最終的には患者様の年齢やADLとも相談となりますが、基本的にはLAACをお薦めいただけると考えております。
腎臓内科医です。心房細動で抗凝固療法中の65歳以上の方は、慢性腎臓病や透析および高血圧があれば HAS-BLED 3点となります。こういった方はたくさんおられますが、みな LAAC の適応になるえる、という理解でよいのでしょうか?また、特にどういった方を紹介すれば患者さんにとって利益があると言えるでしょうか?
CHADS2 スコアの”H”は高血圧で良いのですが、HAS-BLEDスコアの”H”はコントロール不良の高血圧症(収縮期血圧 160mmHg以上)です。慢性腎臓病(CKD)患者さんでは健常腎機能患者さんと比較し、脳梗塞リスクが高いことが知られております。但し、CKD stage4以降ではNOACは慎重投与、stage 5では禁忌となり、ワーファリンへの切り替えが必要となります。現状ガイドラインではワーファリンによる出血リスクが高いこと、虚血性脳梗塞のリスクを減らすというエビデンスに乏しいため、脳梗塞2次予防・人工弁置換術後などの症例に限られております。血液透析患者さんに対するLAACはエビデンスに乏しいですが、有効と考えており、積極的に行なっておりますので、是非ご相談ください。
整形外科医です。心房細動で抗凝固療法中の65歳以上の方で、膝や腰の痛みで NSAID を服用している方を大勢見ております。LAAC の適応ですか?また、痛み止めに湿布薬は含まれますか?
HAS-BLEDの”D”にNSAIDが含まれますが、定期内服が必要な病状であればカウントされます。一時的な内服であれば含みません。また、湿布などの外用薬は含まれません。
出血リスクの高い手術を予定しております。LAAC を行って頂き、抗凝固薬を中止できる環境にして頂きたいのですが、適応はありますか?
術前休薬のための左心耳閉鎖治療は、もともと左心耳閉鎖術の適応があること・その術式が比較的待機的に手術可能であることなどの条件があります。基本的には術後抗血栓療法がある程度の期間必要であり、術後45日程度経過を診る必要があるかと思います。過去に周術期の休薬で脳梗塞イベントを生じたなどの非常にハイリスクは症例では、検討されるかと思います。
WATCHMAN などの閉鎖デバイスは金属製と聞いています。腐食しませんか?
WATCHMANのフレームはナイチノールという金属を使用しており、これはその他の生体内に植え込む多くのデバイスに使用されているものです。安全性に関しては問題ないものと認識しております。
WATCHMAN などの閉鎖デバイスは将来的に入れ替えが必要ですか?
基本的には植え込み後に医学的に問題がない場合には摘出や入れ替えなどの処置は必要ではありません。1回の治療で生涯を通じた脳塞栓予防効果が期待されます。
WATCHMAN などの閉鎖デバイスは MRI は撮影可能ですか?
MRI撮影に関しての制限はありません。いつでも受けていただきます。
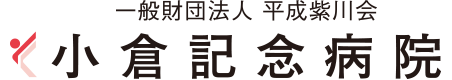

 もどる
もどる